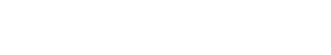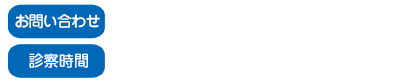こんにちは!
看護師の難波です![]()
先日、京都で行われた獣医学セミナーの看護師向けのプログラムに参加してきました!
いくつかの講義を聞いていたのですが、
1番気になっっていたのは、誤飲についての講義です![]()
 SOS!
SOS!
最近、当院でも石や骨、針など異物を飲み込んでしまったと
来院されたわんちゃんねこちゃんがいらっしゃいました![]()
異物を飲み込んでしまった場合、飲み込んで時間が経過していなく
大きく、尖っていないものなら催吐処置をして胃の中のものを吐かせます。
それでも、異物を吐きださない子は麻酔をかけて内視鏡で
口から胃カメラをいれて異物を探しに行ったり、
最悪、開腹手術になる事もあるんです![]()
そして誤飲のなかでも一番危険なのはひも状異物です![]()
お歳暮のハムに巻かれているおいしい味のついた糸やビニール紐
猫ちゃんの場合ひもで遊んでいで、誤って飲み込んでしまうことも・・・。
糸が腸で詰まってしまうと引きつれてしまい、その力で腸が切れてしまいます。
なので、お尻からひもがでてるのを無理に引っこ抜いたりするのは
とっても危険なんです![]()
ひも状異物の場合は催吐処置はかけず、すぐに開腹手術になります![]()
後は、花粉症の時期でティッシュをたくさん使われる方も
多いのではないでしょうか??![]()
特に鼻に優しく作られている高級な柔らかいティッシュは、
砂糖を使って柔らかくしているため、
わんちゃんにとっては甘くておいしいおやつになることも・・・
ティッシュも意外とつまりやすいんです![]()
では誤飲をどうやって防げばいいのでしょうか?
1.口にしそうなものを置かない。
やはり、これが1番大事です!
長時間の留守で目が届かないときはクレートやサークルの中でお留守番させるのも
誤飲防止対策になります![]()
2.口にしても騒がない。
「食べたらあぶない!」「早く取り上げないと!」と思いがちですが
取り上げようとすると、取られまいと急いで飲み込もうとしてしまいます。
また、騒いでしまうとワンちゃんは「かまってくれた!」「こっちに来てくれた!」
と、その行動が嬉しい報酬となってしまい
口に入れるという行動を繰り返してしまう子もいるそうです。
なので、騒がず落ち着いて、ほかのおもちゃやおやつで
口にしている物から気を反らしてあげるのもいいかもしれませんね![]()
3.「貸して」の練習をしておく。
これは出来ればですが、いざという時これを覚えていると
飲み込む前に口から出させやすいですね![]()
長くなりましたが、
もし危険なものを食べてしまったら、すぐに病院にご連絡くださいね![]()
![]()